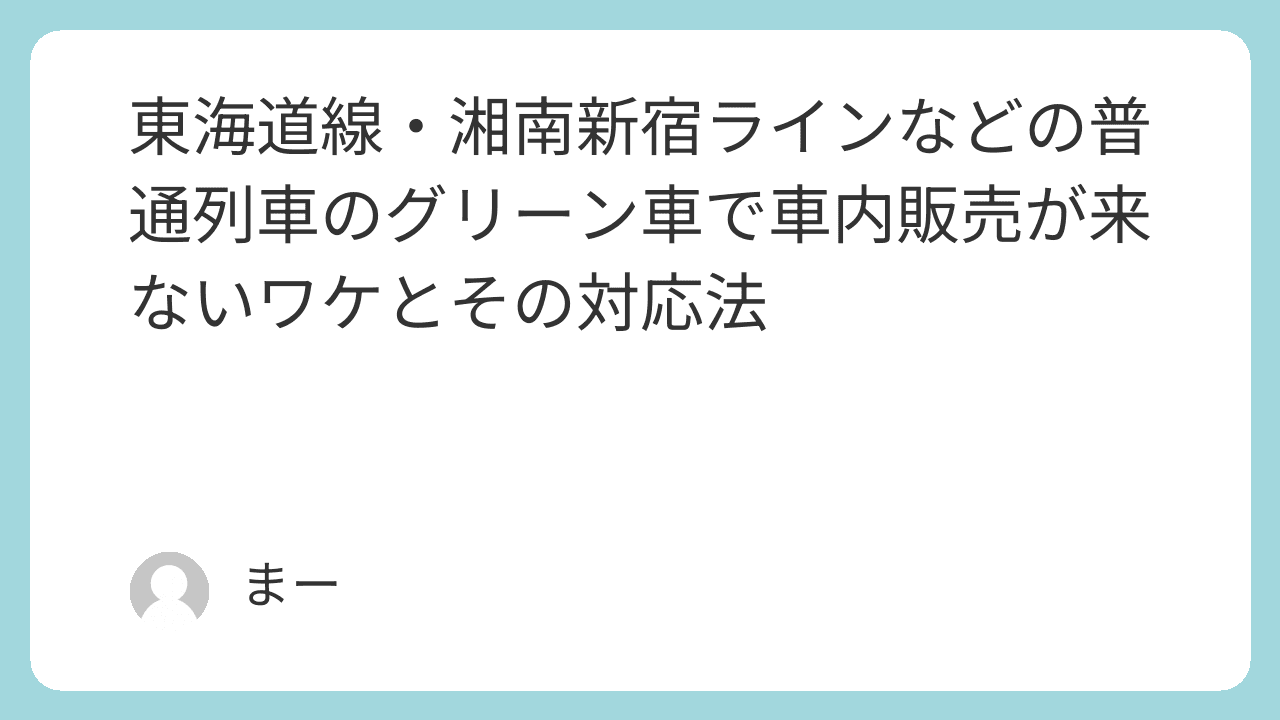グリーン車に乗ると、座ったままでお弁当や飲み物が買えるのを楽しみにしている人も多いと思います。
ですが最近、「東海道線のグリーン車に乗ったのに販売がなかった」「湘南新宿ラインでも販売スタッフを見かけなかった」といった声が目立つようになってきました。事前にグリーン券を買って、車内販売があると期待していた人にとっては残念に感じることもあるでしょう。
この記事では、東海道線や湘南新宿ラインといった普通列車のグリーン車で、なぜ車内販売が来ないことがあるのかをわかりやすく説明します。
あわせて、どんな商品があるのかや、販売スタッフが来ないときにとれる行動もご紹介します。
グリーン車で販売スタッフが来ない主な理由

スタッフが集まらない状況が続いている
以前は東海道線や湘南新宿ラインなどのグリーン車でも、車内販売をよく見かけました。
けれども、最近はその姿をほとんど見かけなくなりました。
大きな理由のひとつが、販売を担当する人の数が足りないことです。
特に都市部を走る通勤路線では、たくさんの人がグリーン車を利用する一方で、販売スタッフの確保が難しくなってきています。
このため、サービスの継続が難しくなり、販売をやめる列車が増えています。
JR東日本でも、販売サービスを一部の新幹線や特急列車にしぼる方針を進めていて、普通列車のグリーン車ではスタッフの配置が減っているのが現状です。
販売が成り立ちにくくなっている
もうひとつの理由は、グリーン車での販売があまり利用されなくなってきている点です。
通勤や通学が中心の東海道線や湘南新宿ラインでは、特急列車や新幹線に比べて、もともと車内販売の利用が少なめでした。
さらに、駅ナカのコンビニや自動販売機が増えたことで、乗る前に飲み物や食べ物を買う人が増え、車内での需要が減ってきました。
また、最近ではキャッシュレスでの支払いが当たり前になってきており、それに対応するためのシステム整備も費用がかかります。
利用者が減っているうえに、そうした準備にもコストがかかるため、販売を続けるのが難しくなってきているのです。
全国的にサービスが縮小されている
実は、こうした流れは東海道線や湘南新宿ラインに限った話ではありません。
JRの各社が、車内販売の規模を小さくしていく方針を打ち出しています。
このため、グリーン車を利用する際には、あらかじめ飲み物や食べ物などを買っておくなど、自分で準備しておくことがより大切になってきています。
車内販売が減ったのはJR東日本の方針転換も関係

グリーン車での販売がほとんどなくなった理由のひとつに、JR東日本がサービスの見直しを進めていることがあります。
効率を重視する流れの中で、コストのかかる販売サービスを縮小する動きが強まりました。
以前は普通列車のグリーン車でも販売が行われていましたが、今では一部の新幹線や特急に絞ってサービスを続ける方向へと変わっています。
これは、実際の利用数やニーズを見て判断されたもので、「よく使われる場所にサービスを集中させる」という考え方です。その結果、東海道線や湘南新宿ラインなどの普通列車では、ほとんど車内販売がなくなってしまいました。
特に、新型コロナウイルスの影響で、人との接触を減らす必要が出てきたこともあり、この流れが一気に加速しました。
そのため、グリーン車に乗っても「販売スタッフが来ない」と感じることが多くなっているのです。
グリーン車で販売されていた商品ってどんなもの?

以前、JR東日本の普通列車グリーン車では、座席までスタッフが来て飲み物や軽食を販売していました。
よく売れていたのは、お茶や缶コーヒー、ビールといった飲み物です。中には、その場で入れてくれるあたたかいコーヒーもあり、楽しみにしていた人も多くいました。
食べ物では、パンやサンドイッチ、ちょっとしたお菓子など、手軽につまめるものが中心でした。
駅で買い忘れても車内で買えるという安心感がありました。
ときには、季節限定のスイーツやその地域だけの特別メニューが登場することもあり、旅行客から注目を集めていました。
しかし今では、東海道線や湘南新宿ラインのような普通列車のグリーン車では、そういった車内販売はほとんど行われなくなっています。そのため、「せっかく楽しみにしていたのに何も買えなかった」とがっかりしてしまうこともあります。
そうならないように、あらかじめ準備をしておくことが大切です。
車内販売がないときのための準備と工夫
東海道線や湘南新宿ラインのグリーン車では、販売スタッフが来ないことが多くなっています。
そのため、事前に必要なものを用意しておくのが安心です。
いちばん簡単な方法は、電車に乗る前に駅の売店やコンビニで飲み物や軽食を買っておくことです。
最近の駅には品ぞろえ豊富なお店が増えていて、お弁当やおにぎりなどもすぐに手に入ります。
移動時間が長くなりそうな場合には、保冷機能のあるボトルホルダーや小さめの保冷バッグを使うと便利です。冷たい飲み物や食べ物をしばらく新鮮なままで持ち歩けます。
また、ラッシュの時間帯などで混雑が予想されるときには、あらかじめ一口サイズのお菓子や食べやすい軽食を持っていくのもおすすめです。座席を立ちにくいときでも、手元で手軽に食べられるようにしておくと安心です。
さらに、車内販売があるかどうかを調べてから乗車するのもひとつの方法です。JR東日本の公式アプリやホームページでは、列車ごとの販売情報が確認できます。
「あると思ってたのに、なかった」という失敗を防げます。
急に電車に乗ることになったときに備えて、よく使う駅の売店や自動販売機の場所を覚えておくのもおすすめです。たとえば、東海道線の品川駅や横浜駅、湘南新宿ラインの新宿駅や池袋駅など、大きな駅なら短い時間で飲み物や軽食を買うことができます。
通勤や通学などで普段からグリーン車を使う人なら、家から水筒やおやつを持っていくのを習慣にするのも良い方法です。健康にもお財布にもやさしいので、毎日のちょっとした工夫として取り入れてみてください。
グリーン車の車内販売はどうなっていく?これからの動きと予想
これまで、普通列車のグリーン車での車内販売はどんどん少なくなってきました。
では、今後このサービスが復活することはあるのでしょうか。
実はJR東日本では、今「必要なところにしぼって効率よくサービスを行う」という方針のもと、新幹線や一部の特急列車でもサービス内容の見直しが進められています。
最近では、販売スタッフが乗らない代わりに自動販売機を設置したり、スマートフォンのアプリから注文して自分で取りに行くスタイルが広まりつつあります。
JR東日本でもこうした「セルフ販売」の仕組みを一部の列車で試しており、利用者の反応や採算がどうかを見ながら、今後ほかの路線にも広げていくか検討中です。
また、キャッシュレス決済やモバイル注文がもっと身近になることで、よりスムーズに買い物ができるようになるかもしれません。こうした便利な方法が広まれば、違った形での車内販売が戻ってくる可能性もあるでしょう。
ただし、JR東日本ではコストや利用状況をしっかり見極めながら判断しているため、すぐに全てのグリーン車で販売が復活するとは考えにくいです。
だからこそ、利用者側としては「販売があればラッキー」という気持ちで、必要なものは事前に準備しておくことが大切です。
まとめ
東海道線や湘南新宿ラインのグリーン車で販売スタッフを見かけなくなった理由には、スタッフ不足、買う人の減少、そしてJR東日本によるサービスの見直しなど、いくつかの要因が関係しています。最近は車内販売が減ってきているため、事前に飲み物や軽食を駅で買っておくことが大切です。
また、乗る前にJR東日本のアプリやホームページを使って、販売サービスがあるかどうかを確認しておくのもおすすめです。長時間の移動になるときは、保冷グッズなどを使って飲み物や食べ物を持ち運べば、より快適に過ごせます。
今後、販売サービスが新しい形で戻ってくる可能性もありますが、現時点では「サービスがない前提」で準備をしておくのがベストです。自分に合った工夫をしながら、グリーン車での時間を気持ちよく過ごしましょう。